〒596-0054 大阪府岸和田市宮本町41-1 ツキシロビル3F
営業時間:9:00~20:00
(土日祝日も対応可)
時効の中断(時効の更新)とは
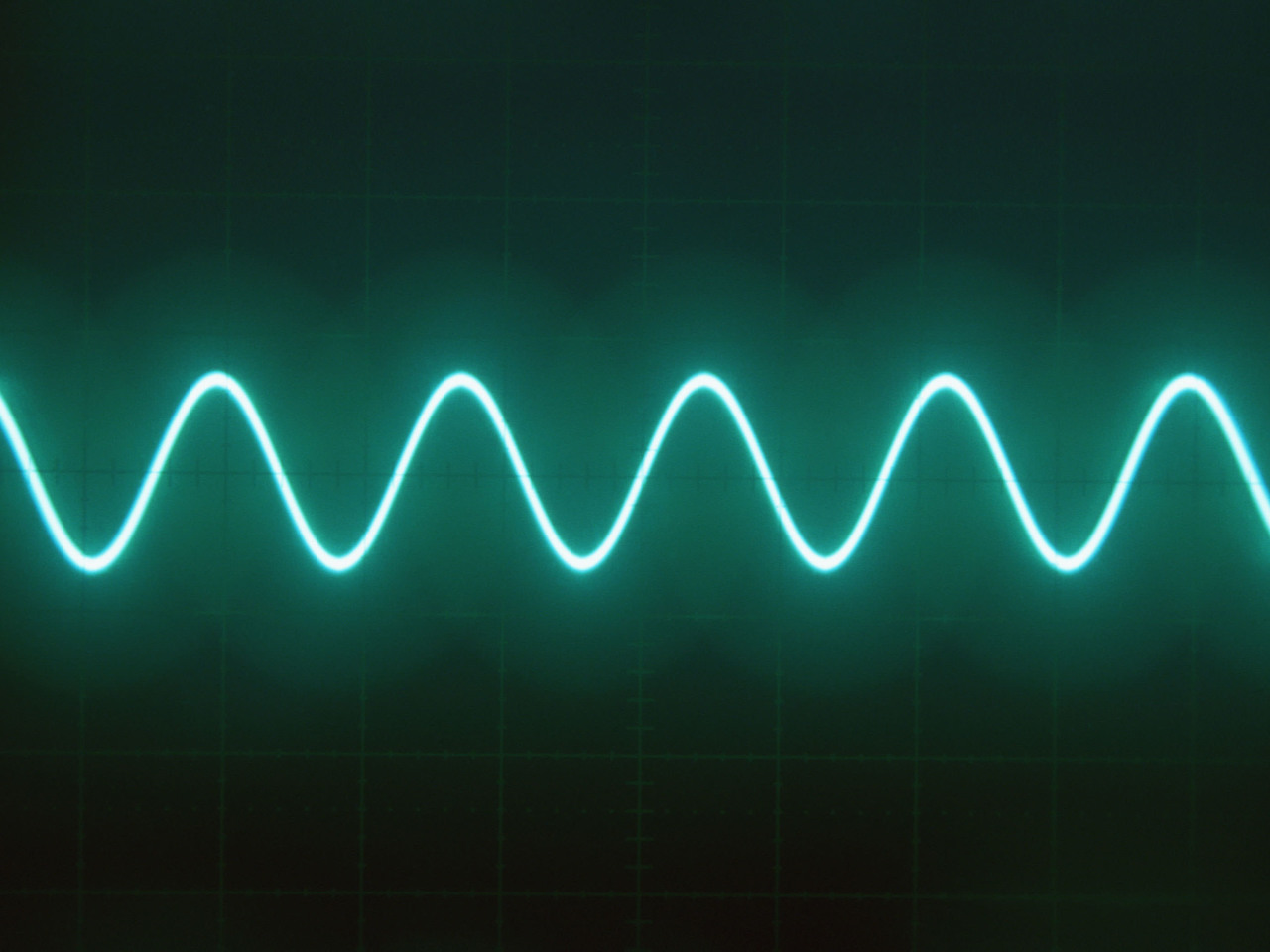
さまざまな契約の消滅時効期間が進行していくのを止める目的で、債権者が権利を行使する場合があります。時効の進行がリセットする効果のことを「時効の中断(改正民法では「時効の更新」)」と言い、時効の中断(時効の更新)を生じさせる事由を「時効中断事由」と言います。旧民法にて定める時効中断事由としては、「請求」、「差押・仮差押・仮処分」、「承認」の三つがあります。
「請求」とは、債権者から債務者に対し、裁判上の請求をすることを言います。裁判上の請求をしても、債権者の都合で途中で取り下げたりした場合は、原則として時効中断の効果はありません。なお、債権者から債務者に対し、通常の催告行為をおこなうことを「催告」と言いますが、時効を中断させるためには催告した後、6ヶ月以内に「請求」をおこなう必要があります。
「差押・仮差押・仮処分」とは、債権者が債務者の財産に対し、差押えや仮差押え、仮処分の手続きをおこなうことを指します。
「承認」とは、債務者が債権者に対し、債務承認行為をおこなうことを言います。例えば、債務を返済したり、債務確認書等を締結したりする行為です。
時効が中断(更新)すると、消滅時効期間の進行はリセットして、最初から消滅時効期間が進行していくことになります。消滅時効期間がリセットされた場合でも、消滅時効期間が進行した結果、各法律にて定める消滅時効期間が経過すれば、時効援用手続きは可能です。
なお、時効の中断とは別に、一定の場合に時効の完成が猶予される「時効の停止(改正民法では「時効の完成猶予」)」という制度があります。
次はこちら
お問合せ・ご相談
担当:仲
受付時間:9:00~20:00
(土日祝日も対応可)
行政書士スカイ法務事務所は、借金や各種債務[消費者金融会社や債権回収会社(サービサー)に対する債務、携帯電話料金、医療費、家賃、NHK受信料、売掛金、個人間の借金など]の時効援用手続きを専門としており、東京や横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡はもちろん北海道から沖縄まで日本全国に対応いたします。債務(借金)の時効援用手続きに関する無料相談を実施していますので、お気軽にお問い合わせください。行政書士は、法律で守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
無料相談実施中

お電話でのお問合せ・相談予約
ご相談は無料です
<受付時間>
9:00~20:00
(土日祝日も対応可)
- サービス案内
- 事務所紹介
- お問合せ・お見積り
主な業務地域
[北海道 時効援用] [青森県 時効援用] [岩手県 時効援用] [宮城県 時効援用] [秋田県 時効援用] [山形県 時効援用] [福島県 時効援用] [新潟県 時効援用] [茨城県 時効援用] [群馬県 時効援用] [栃木県 時効援用] [埼玉県 時効援用] [東京都 時効援用] [千葉県 時効援用] [神奈川県 時効援用] [山梨県 時効援用] [長野県 時効援用] [富山県 時効援用] [石川県 時効援用] [福井県 時効援用] [静岡県 時効援用] [愛知県 時効援用] [岐阜県 時効援用] [三重県 時効援用] [大阪府 時効援用] [京都府 時効援用] [滋賀県 時効援用] [兵庫県 時効援用] [奈良県 時効援用] [和歌山県 時効援用] [鳥取県 時効援用] [島根県 時効援用] [岡山県 時効援用] [広島県 時効援用] [山口県 時効援用] [徳島県 時効援用] [香川県 時効援用] [愛媛県 時効援用] [高知県 時効援用] [福岡県 時効援用] [佐賀県 時効援用] [長崎県 時効援用] [熊本県 時効援用][大分県 時効援用] [宮崎県 時効援用] [鹿児島県 時効援用] [沖縄県 時効援用] [札幌市 時効援用] [仙台市 時効援用] [東京都中央区 時効援用] [東京都台東区 時効援用] [東京都墨田区 時効援用] [東京都品川区 時効援用] [東京都目黒区 時効援用] [東京都世田谷区 時効援用] [東京区杉並区 時効援用] [東京都足立区 時効援用] [東京区葛飾区 時効援用] [東京都江戸川区 時効援用] [東京都北区 時効援用] [新潟市 時効援用] [東京都新宿区 時効援用] [東京都渋谷区 時効援用] [東京都港区 時効援用] [東京都中野区 時効援用] [東京都練馬区 時効援用] [東京都文京区 時効援用] [東京都豊島区 時効援用] [横浜市 時効援用] [千葉市 時効援用] [さいたま市 時効援用] [川崎市 時効援用] [町田市 時効援用] [静岡市 時効援用] [松本市 時効援用] [名古屋市 時効援用] [津市 時効援用] [岐阜市 時効援用] [西脇市 時効援用] [草津市 時効援用] [富山市 時効援用] [京都市 時効援用] [大阪市 時効援用](中央区 時効援用)(西区 時効援用)(北区 時効援用)(福島区 時効援用)(此花区 時効援用)(港区 時効援用)(大正区 時効援用)(住之江区 時効援用)(住吉区 時効援用)(東住吉区 時効援用)(平野区 時効援用)(阿倍野区 時効援用)(西成区 時効援用)(浪速区 時効援用)(天王寺区 時効援用)(生野区 時効援用)(東成区 時効援用)(城東区 時効援用)(鶴見区 時効援用)(都島区 時効援用)(旭区 時効援用)(淀川区 時効援用)(東淀川区 時効援用)(西淀川区 時効援用)[堺市 時効援用] [高石市 時効援用] [泉大津市 時効援用] [和泉市 時効援用] [岸和田市 時効援用] [貝塚市 時効援用] [泉佐野市 時効援用] [泉南市 時効援用] [阪南市 時効援用] [茨木市 時効援用] [和歌山市 時効援用] [奈良市 時効援用] [白浜市 時効援用] [田辺市 時効援用] [東大阪市 時効援用] [八尾市 時効援用] [守口市 時効援用] [高槻市 時効援用] [枚方市 時効援用] [豊中市 時効援用] [茨木市 時効援用] [神戸市 時効援用] [姫路市 時効援用] [広島市 時効援用] [福山市 時効援用] [松山市 時効援用] [今治市 時効援用] [徳島市 時効援用] [高知市 時効援用] [豊岡市 時効援用] [福岡市 時効援用] [北九州市 時効援用] [飯塚市 時効援用] [熊本市 時効援用] [宮崎市 時効援用] [鹿児島市 時効援用] [那覇市 時効援用] [名護市 時効援用] ほか
